ここから本文です。
平成21年度から適用される個人住民税の税制改正
1.寄附金税制の拡充
前年1月~12月の間に控除対象にあたる寄附をしたかたは、翌年度の住民税所得割から税額控除されます。平成21年度から、この寄附金控除に関するしくみが大きく変わります。
寄附金の適用下限額の引き下げ
寄附金の適用下限額が、10万円→5千円に引き下げられました。
税制改正により、平成23年1月1日以降に支払する寄附金から適用下限額が5千円から2千円に引き下げられました。
寄附金の控除対象限度額の引き上げ
総所得金額等の30パーセント(以前は25パーセント)に引き上げられました。
所得控除から税額控除に変更
寄附金の控除が、これまでの「所得控除」から「税額控除」に変わります。
税額控除額の求めかた
税額控除額=【対象となる寄附金(総所得金額等の30パーセントを限度)-5千円】×税率(市6パーセント・県4パーセント)
控除対象となる寄附金の拡大
平成20年度まで住民税において寄附金控除の対象だった地方公共団体、住所地の都道府県共同募金会、日本赤十字社の支部に、所得税の控除対象寄附金のうち、千葉県及び柏市が条例指定した法人が加わりました。
柏市が条例指定した法人
- 柏市内に主たる事務所(法人本部)がある独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、認定特定非営利活動法人(国税庁長官の認定を受けたもの)
- 柏市内に学校を設置する国立大学法人・学校法人
- 柏市内で社会福祉事業を行う社会福祉法人
- 特定公益信託への信託財産の寄附(千葉県知事または千葉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行うもの)
(注意)千葉県が条例で指定した法人で、柏市内に事業所等がない場合は、市民税からの税額控除(6パーセント)はありません。県民税(4パーセント)部分のみの税額控除となります。
ふるさと納税の税額控除
都道府県・市町村(地方公共団体)に対して5,000円を超える寄附金(=ふるさと納税)は、個人住民税の所得割の10%を限度に、特例控除が適用になります。
ふるさと納税の税額控除額の求めかた
以下のAとBの合計額が住民税の税額控除となります。
A(基本控除分)
〔寄附金額(総所得金額等の30パーセントを限度)-5,000円〕×10パーセント(市民税6パーセント、県民税4パーセント)
B(特例控除分)
(寄附金額-5,000円)×〔90パーセント-0~40パーセント(所得税の限界税率)〕
(補足)
- 特例控除の割合は、市民税5分の3、県民税5分の2
- 総所得金額等の30パーセント上限は基本控除のみに、所得割の10パーセントの上限は特例控除のみに適用
- 所得税については、累進課税方式がとられており、課税対象所得を数段階に分けて、その区分ごとに異なる税率が課されます。限界税率とは、寄附したかたに適用される所得税率のうち、最大のものを指します。
控除を受けるには?
所得税の確定申告(税務署)を行うことで所得税と住民税の寄附金控除が受けられます。確定申告を行う必要がないかたは住民税申告(市役所)が必要です。申告の際には、各団体が発行する「領収書」または「寄附金受領証明書」を添付してください。
ふるさと納税や所得税で認められている寄附金控除の申告方法について詳しく調べる
関連サイト(新しいウィンドウが開きます)
個人住民税の寄附金税制について詳しく調べる
所得税の寄附金税制について詳しく調べる
2.個人住民税(市・県民税)の公的年金からの引き落とし(特別徴収制度)が始まります
平成21年10月支給分の公的年金から
公的年金(老齢基礎年金等)受給者の納税の便宜や市町村の徴収の効率化を図るため、平成20年4月30日に公布されました「地方税法等の一部を改正する法律」により、平成21年度より公的年金から市・県民税を引き落としさせていただく「特別徴収制度」が開始されます。金融機関へ足を運ぶ手間を省くことができるほか、普通徴収では4回だった納期が年金支給月の6回になることで1回あたりの負担が軽くなります。
4月1日現在65歳以上の年金受給者のうち住民税の納税義務のあるかたが対象です
65歳以上のかたの年金所得にかかる住民税の納税方法が変わります。
この制度の対象となるのは、「4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得にかかる住民税の納税義務のあるかた」です。
ただし、以下のかたについては、対象となりません。
- 介護保険料が年金から引き落としされていないかた
- 引き落とされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超えるかた など
引き落としの対象となる年金とは
老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等を言います。障害年金および遺族年金などの非課税の年金からは、住民税の引き落としはされません。
引き落としされる住民税額は
引き落としされるのは、年金所得の金額から計算した住民税額のみです。給与所得や事業所得などの金額から計算した住民税額は、これまでどおり給与からの引き落とし、または納付書で納めていただくことになります。
引き落としが中止となる場合は
引き落とし開始後、市外への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、引き落としが中止となり、普通徴収(納付書により役所や金融機関などで納める方法)により納めていただくことになります。
平成21年10月支給分の年金から引き落としが始まります
引き落としの開始は、平成21年10月支給分の年金からとなります。そのため、平成21年度の住民税額のうち半分については、平成21年6月と8月に、これまでどおり納付書で納めていただくことになります。
- 総務省ホームページ(外部サイトへリンク)
- 総務省のホームページ(住民税の年金からの引き落としについてのリーフレット)(外部サイトへリンク)
- 総務省のホームページ(公的年金からの特別徴収)(外部サイトへリンク)
(例)住民税の年税額が6万円(年金所得のみ)の場合
| 納付書で納める(普通徴収) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月 | 6月 | 8月 | 10月 | 1月 |
| 税額 | 1万5千円 | 1万5千円 | 1万5千円 | 1万5千円 |
| 算出方法 | 4分の1 | 4分の1 | 4分の1 | 4分の1 |
年税額の4分の1ずつ納付書で納めていただいていました
| 納付書で納める(普通徴収) | 年金からの引き落とし(特別徴収) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 税額 | 1万5千円 | 1万5千円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |
| 算出方法 | 4分の1 | 4分の1 | 6分の1 | 6分の1 | 6分の1 |
6月と8月は年税額の4分の1ずつをこれまでどおり納付書で納めていただきます。10月・12月・2月は年税額の6分の1ずつを引き落とします。
| 年金からの引き落とし(特別徴収) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 税額 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |
| 算出方法 | 前年度2月と同じ額 | 22年度の年税額の残りの3分の1ずつ | ||||
4月・6月・8月は、前年度の2月の税額と同額を引き落とします。10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額を引き落とします。
年金の特別徴収に関するQ&A
![]() 1
1
公的年金からの特別徴収制度導入の目的は何ですか?
![]() 1
1
公的年金の受給者は、現在、普通徴収の対象となっており、各納税義務者がそれぞれ市役所や金融機関の窓口等で納税している。今後の高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給する高齢者は益々増加することが予想されています。
高齢者である公的年金受給者のかたがたの納税の便宜を図ると共に、市町村における徴収の効率化を図る観点から特別徴収制度が創設されました。この制度は、徴収の方法を普通徴収(年4回)から特別徴収(年6回)に変更するものであり、各納税義務者に対しては、新たに税額を増加して負担を強いるものではありません。
![]() 2
2
いつから、どのような年金が特別徴収の対象になるのですか?
![]() 2
2
平成21年度から特別徴収が実施されますが、上半期の4月から9月までは、普通徴収の方法により各個人で1期分を6月に2期分を8月に金融機関等で納めていただき、10月支給分から特別徴収が実施されます。対象となる公的年金は、老齢基礎年金等(老齢又は退職を支給事由とする年金)です。
![]() 3
3
公的年金からの特別徴収の実施については、本人の意思による選択はできますか?
![]() 3
3
地方税法第321条の7の2において、公的年金所得に係る個人住民税については、年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされておりますので原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が対象となっています。
給与からの特別徴収においても、本人による選択は認められておらず、これと同様の取扱いとなっています。
![]() 4
4
後期高齢者医療保険制度においては、特別徴収制度の見直し(口座振替による普通徴収の選択制)がおこなわれていますが、個人住民税では、そのようなことはないのですか?
![]() 4
4
現在のところ個人住民税については、見直し等は予定されておりませんので予定通り、平成21年10月支給分の公的年金等から実施されることになります。
![]() 5
5
給与及び年金からそれぞれ特別徴収される場合で、給与、公的年金所得以外の所得(不動産所得など)に係る税額も特別徴収にする場合、給与又は年金のいずれかを選ぶのに優先順位はありますか?
![]() 5
5
給与所得、公的年金所得以外の所得に係る税額の年金からの特別徴収税額への加算は、当面実施されませんので、給与所得、公的年金所得以外の所得に係る税額については、給与からの特別徴収か個人で納税する普通徴収かを所得税の確定申告の際、選択することとなります(下表「確定申告書第2表「住民税に関する事項」」参照)。
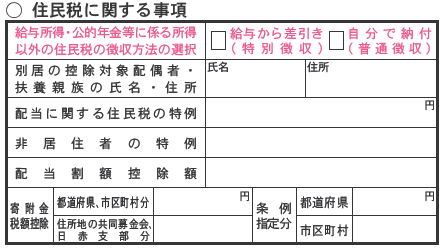
![]() 6
6
公的年金には、企業年金など厚生労働大臣(日本年金機構)(※)等からの年金以外の年金もありますが、このような企業年金や恩給などの公的年金等収入は、特別徴収税額を決定するための所得に入りますか?
(補足)社会保険庁は平成21年12月末をもって廃止されました
![]() 6
6
特別徴収の対象となる「公的年金等に係る所得に係る所得割額」は、企業年金等の年金や恩給などを含めた公的年金等全てを合算して計算した税額をいいますので他の公的年金等も含まれます。
![]() 7
7
年金所得の他に営業所得のマイナスのみがあった場合、損益通算しないと正しい税額が算出できないと思いますが損益通算(マイナス)はできますか?
![]() 7
7
できます。損益通算を行なうことにより年税額を算出し、公的年金から算出年税額を特別徴収することになります。
![]() 8
8
私は4月1日現在65歳で、年金収入があり会社勤めをしています。住民税の納付方法について教えてください。
![]() 8
8
特別徴収を開始する初年度は、以下のようになります。
給与所得にかかる税額は、引き続き給与からの特別徴収(6月~翌年5月までの年12回)で納付(均等割、所得割)
平成20年4月30日に公布されました「地方税法等の一部を改正する法律」により、65歳以上のかたの公的年金等に係る住民税は、給与からの特別徴収はできなくなりました。特別徴収を開始する初年度は、6月に納税通知書を送付しますので上半期の1期、2期分は普通徴収で自身で納付していただき、10月以降の下半期分は年金からの特別徴収(10月、12月翌年2月の3回徴収)により納付となります。
![]() 9
9
私は63歳で年金収入があり現在会社勤めをしています。住民税は年金収入と給与収入を合わせて会社から特別徴収をしています。65歳以上の人は年金から住民税を特別徴収すると聞いておりますが、65歳未満の私は、引き続き給与からの特別徴収はできますか?
![]() 9
9
従来、年金所得と給与所得があるかたで、年金にかかる所得を含めた住民税を給与所得からの特別徴収の方法で納付していたかたにつきましては、20年度税制改正で、年金分を含めた住民税は給与からの特別徴収ができなくなりました。
22年度税制改正では、徴収方法の見直しが行われ65歳未満の公的年金等の所得を有する給与所得者については、前回の制度改正前の状況と同様になりましたので、公的年金の所得に係る税額も給与所得に係る税額と合わせて給与から特別徴収することができるようになりました。
65歳未満で公的年金等に係る所得を有する給与所得者の方の徴収方法の改正について詳しく調べる
平成20年度から引き続きのもの
平成21年度市・県民税に関する住宅ローン控除の調整措置について詳しく調べる
関連サイト
お問い合わせ先