ここから本文です。
平成22年度から適用される個人住民税の税制改正
65歳未満で公的年金等に係る所得を有する給与所得者のかたの徴収方法の改正
平成20年度税制改正において、65歳以上の公的年金等の受給者で年金所得に係る住民税の納税義務のあるかたは、年金から特別徴収の方法によることとされ、特別徴収の対象とならない65歳未満で公的年金等の所得を有する給与所得者については、公的年金等の所得に係る税額は給与所得に係る税額に加算して、給与から特別徴収することができなくなりました。
これにより、65歳未満の方の公的年金等の所得に係る住民税は、普通徴収(納付書や口座振替等による納付)の方法により、金融機関等の窓口で納付するという手間が新たに発生することになりました。
平成22年度税制改正では、この納付方法についての見直しが行なわれ、65歳未満で公的年金等に係る所得を有する給与所得者については、給与所得、年金所得以外の所得に係る税額と同様に、公的年金等の所得に係る税額も給与所得に係る税額に加算して特別徴収することができるようになりました。
このことにより、平成22年度以降は、原則として65歳未満のかたの公的年金等の所得に係る住民税については、給与所得に係る税額と合わせて、給与からの特別徴収の方法により徴収させていただくことになります。
また、本人の申し出により、昨年と同様に普通徴収の方法による納付もできますので、普通徴収を希望されるかたは市民税課まで連絡をお願いします。
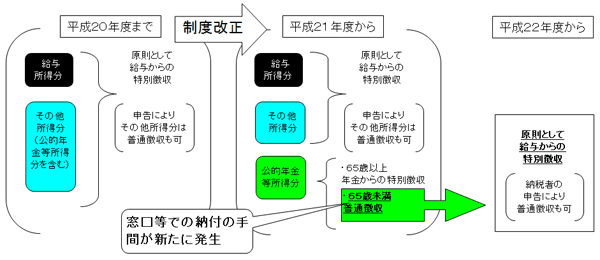
平成22年度分の個人市・県民税から新たな住宅ローン控除が創設
平成21年から平成25年末までに入居し、所得税の住宅借入金等特別税額控除(以下住宅ローン控除)を受けるかたで、所得税から控除しきれなかった額が発生した場合は、翌年度の個人市・県民税(所得割)から控除される制度が創設されました。なお、適用に際し、本市への申告は不要です。
(補足)初めて住宅ローン控除の適用を受けるかたは、税務署での確定申告が必要となります
また、平成11年から平成18年末までに入居し、個人市・県民税の住宅ローン控除を受けるかたについて、平成21年度までは本市への申告が必要でしたが、この制度創設に伴い、平成22年度から本市への申告が原則不要になりました。
1 控除の対象となるかた
平成11年から平成18年末まで、または平成21年から平成25年末までに入居し、前年分(平成21年分以降)の所得税の住宅ローン控除を受けた方で、控除しきれなかった額があるかた。
(補足)
平成19年または平成20年に入居されたかたについては、個人市・県民税からの住宅ローン控除の適用とはなりません
これは、住宅ローン減税の効果を確保することができるよう、所得税の住宅ローン控除の控除率を引き下げる一方で、
控除期間を10年から15年に選択できる特例措置が設けられているためです。
関連サイト(新しいウィンドウが開きます)
タックスアンサー「マイホームの取得等と所得税の税額控除」(国税庁のホームページ)(外部サイトへリンク)
2 控除額
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額
(限度額97,500円 内訳=市民税58,500円、県民税39,000円)
1.2.のいずれか少ない金額
(補足)この額が0円になる場合は、個人市・県民税への住宅ローン控除の適用はありません
3 住宅ローン控除を個人市・県民税に適用するには
個人市・県民税の住宅ローン控除の申告を市にしていただく必要は、原則ありません。
年末調整で所得税の住宅ローン控除を受けたかたへ
給与所得者のかたが個人市・県民税について住宅ローン控除の適用を受けるには、毎年1月頃に配付される「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が正しく記載されている必要があります。記載がなければ個人市・県民税に住宅ローン控除が適用されませんので、必ずご確認のうえ、記載がない場合は、お勤め先の給与担当部署にお問い合わせ下さい。
住宅ローン控除の対象となるかどうかを、平成21年分の源泉徴収票から見分けることができます。
(注意)下記の源泉徴収票は平成21年分の例となります。【居住開始年月日】は平成21年から平成25年末までの方も対象となります。
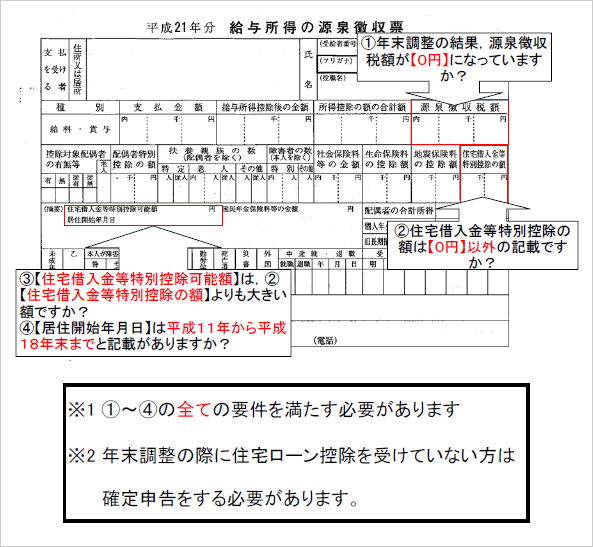
確定申告をされるかたへ
住宅ローン控除を初めて申告する場合、住宅ローン控除を年末調整で受けていない場合は、その確定申告をもって個人市・県民税の住宅ローン控除を適用しますので、確定申告書を税務署に提出してください。
(注意)確定申告書第2表「特例適用条文等」欄には、必ず居住開始年月日をご記入ください。
住宅ローン控除の対象となるかどうかを、平成21年分の確定申告書から見分けることができます。
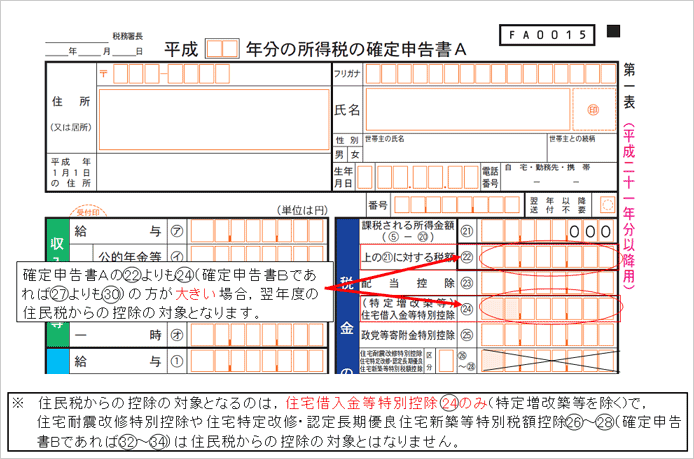
4 住民税の控除の対象にならない住宅ローン控除
特定増改築等(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事など)に係る住宅ローン控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定長期優良住宅新築等特別税額控除は除かれます。
関連サイト(新しいウィンドウが開きます)
2.証券税制改正の概要
1 上場株式等に係る配当・譲渡所得等に対する軽減税率の延長
平成15年1月1日から平成20年12月31日までの間に行われる譲渡による上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して、申告分離課税により課される個人住民税所得割の税率については、3パーセント(市民税1.8パーセント、県民税1.2パーセント)の軽減税率とする特例措置が、平成23年12月31日まで延長されました。
本則税率5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)となります。
| 平成20年12月まで | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年1月以降 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税率 | 10パーセント (住民税3パーセント、所得税7パーセント) |
10パーセント(住民税3パーセント、所得税7パーセント) | 20パーセント(住民税5パーセント、所得税15パーセント) | ||
税制改正により上場株式等に係る配当・譲渡所得等に対する軽減税率の特例措置が平成25年12月31日まで2年延長されました。
2 上場株式等に係る配当所得の申告分離課税制度の創設
平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等を有する場合において、当該上場株式等に係る配当所得の金額については申告分離課税を選択できる制度が創設されました。
この場合において、申告する上場株式等に係る配当所得の金額の合計額について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択適用とすることとし、総合課税を選択した場合には配当控除の適用を受けることができますが、申告分離課税を選択した場合には配当控除の適用を受けることができません。
| 平成20年12月31日まで | 平成21年1月1日から 平成23年12月31日まで |
平成24年1月1日以降 | |
|---|---|---|---|
| 総合課税 | 累進税率 (所得税5~40パーセント、住民税10パーセント)(注意1) |
||
| 申告分離課税 | - | 10パーセント (所得税7パーセント、住民税3パーセント)(注意2) |
20パーセント (所得税15パーセント、住民税5パーセント)(注意3) |
(注釈)
- 住民税10パーセントの内訳 市民税6パーセント、県民税4パーセント
- 住民税3パーセントの内訳 市民税1.8パーセント、県民税1.2パーセント
- 住民税5パーセントの内訳 市民税3パーセント、県民税2パーセント
税制改正により上場株式等に係る配当・譲渡所得等に対する軽減税率の特例措置が平成25年12月31日まで2年延長されました。
3 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算特例の創設
平成22年度分以後の個人住民税については、前年分の上場株式等の譲渡損失または前年以内3年の譲渡損失があるとき「申告分離課税」を選択した上場株式等の配当所得との間で損益通算ができる特例が創設されました。また、源泉徴収選択口座を活用した方式については、平成22年1月1日から適用となります。
| 平成20年分まで | 平成21年分(22年度) | 平成22年(23年度)以降 |
|---|---|---|
| 損益通算不可 | 確定申告により損益通算可 | |
| ― | 源泉徴収選択口座において損益通算可 | |
関連サイト(新しいウィンドウが開きます)
お問い合わせ先