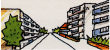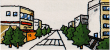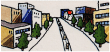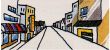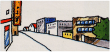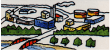ここから本文です。
柏市のまちづくり(土地利用)
1.市街化区域と市街化調整区域
都市の無秩序な市街化を防止し、健全で計画的な市街化を図るため、都市計画区域を市街地を積極的に整備する区域(市街化区域)と市街化を抑制する区域(市街化調整区域)とに区分し、各区域について、整備、開発又は保全の方針を都市計画に定めています。
市街化区域は、既に市街地を形成している区域及びその周辺で優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、用途地域を定め、道路、公園、下水道など市街地整備の基盤となる都市施設の計画的な整備を図る区域です。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域であり、市街化を促進するような都市施設の整備は原則的に行いません。
本市では、昭和45年7月31日に市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画(いわゆる線引き)を行いました。

市街化区域(右側)と市街化調整区域(左側)
(柏都市計画区域)
市街化区域5,484ヘクタール、市街化調整区域6,006ヘクタール
(令和3年3月末現在)
2.地域地区
地域地区は、都市における土地利用の計画を実現していくための規制や誘導を行い、土地の自然的条件や土地利用の動向を検討し、住居、商業、工業その他の用途を適正に配分することにより、都市機能の維持、住環境の保護、商業・工業等の利便の増進、美観風致の維持、公害の防止など都市環境を保持するために定めています。
本市では、用途地域、高度地区、高度利用地区、防火地域及び準防火地域、生産緑地地区などを定めています。
(1)用途地域
用途地域は、地域地区の根幹をなすものであり、将来のあるべき土地利用の姿を実現するための一つの手段として、建築物の用途、容積、形態を定め地域の性格を明らかにするとともに、良好な都市環境の保全、育成に努め、都市の健全な発展を図ることを目的として定めています。
(補足)
柏市の都市計画決定一覧へ
|
区分 |
イメージ |
制限等 |
|---|---|---|
|
第一種低層住居専用地域 |
|
低層住宅の良好な環境を守るための地域です。 小規模な店舗や事務所をかねた住宅や小中学校などが建てられます。 |
|
第二種低層住居専用地域 |
|
主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。 小中学校などのほか、150平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。 |
|
第一種中高層住居専用地域 |
|
中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。 病院、大学、500平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。 |
|
第二種中高層住居専用地域 |
|
主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。 病院、大学などのほか、1,500平方メートルまでの一定のお店や事務所などが建てられます。 |
|
第一種住居地域 |
|
住居の環境を守るための地域です。 3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。 |
|
第二種住居地域 |
|
主に住居の環境を守るための地域です。 店舗、事務所、ホテル、ぱちんこ屋、カラオケボックスなどは建てられます。 |
|
準住居地域 |
|
道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、 これと調和した住居の環境を保護するための地域です。 |
|
近隣商業地域 |
|
近隣の住民が日用品の買い物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域です。 住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。 |
|
商業地域 |
|
銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業等の業務の利便の増進を図る地域です。 住宅や小規模の工場も建てられます。 |
|
準工業地域 |
|
主に軽工業の工場等の環境悪化の恐れのない工業の業務の利便を図る地域です。 危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。 |
|
工業地域 |
|
主として工業の業務の利便の増進を図る地域で、どんな工場でも建てられます。 住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。 |
|
工業専用地域 |
|
専ら工業の業務の利便の増進を図る地域です。 どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。 |
(2)容積率・建ぺい率
容積率
建築物の延床面積の、敷地面積に対する割合。
敷地の前の道路が狭い場合は、都市計画などで指定された率よりもさらに制限されることがあります。
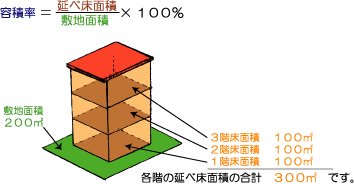
(例)敷地面積200平方メートル、容積率150%の場合に建てられる建物の延べ床面積の限度は?
延べ床面積=200平方メートル(敷地面積)×150%(容積率)=300平方メートルとなります。
建ぺい率
建築面積の敷地面積に対する割合。
敷地が街区の角にある(角地)場合や、防火地域にある耐火建築物などは緩和されることがあります。
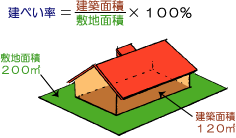
(例)敷地面積200平方メートル、建ぺい率60%の場合に建てられる建物の建築面積の限度は?
建築面積=200平方メートル(敷地面積)×60%(建ぺい率)=120平方メートルとなります。
(3)高度地区
高度地区は、高さの最低限度と最高限度を定めることができますが、本市では隣接する北側宅地への日照、通風などを確保し、都市における良好な住環境を保つため、高さの最高限度を定めており、第一種高度地区と第2種高度地区を決定しています。
(補足)
柏市の都市計画決定一覧へ
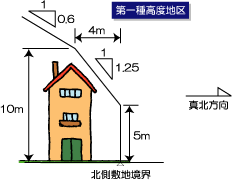
北側宅地に配慮した建築物

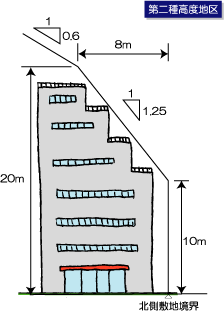
絶対高さ
本市では、第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域の建物の高さの最高限度を10メートルとしています。
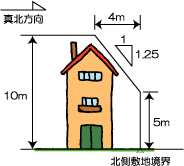
(4)高度利用地区
高度利用地区は、中心市街地など、都市空間を有効に利用し、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るために建築面積の最低限度、容積率の最高・最低限度などを規制する地区です。
(補足)
柏市の都市計画決定一覧へ
(5)防火地域及び準防火地域
防火地域及び準防火地域は、市街地の火災による延焼を防ぐために定めるもので、耐火建築物又は準耐火建築物あるいは防火構造にするなど、防火上の観点から建築規制を行っています。
(補足)
柏市の都市計画決定一覧へ
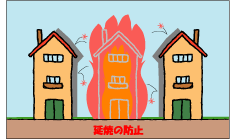

柏駅西口の耐火建築物
防火地域及び準防火地域内の構造制限の概要

- 本表は、建築基準法第61条及び第62条の概要であり、すべての制限について掲載したものではありません
- 耐火建築物とは、壁や柱といった主要構造部を鉄筋コンクリート造等の耐火構造とした建物で、延焼のおそれのある部分に一定の防火設備を設けたものです
- 準耐火建築物とは、耐火建築物に準ずる防火性能を有する建物と、それらと同等の耐火性能を持ち、一定の技術的基準に適合した建物です
(6)生産緑地地区
生産緑地地区は、市街化区域内にある農地等の農業生産活動に裏付けられた緑地機能に着目して、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図る都市計画制度です。
生産緑地に指定されると、農地として管理することが義務付けられ、農地以外の利用はできなくなりますが、税制上の優遇措置を受けることができます。
(補足)
柏市の都市計画決定一覧へ
(7)地区計画
地区計画は、地区のみなさんで話し合って、建物の用途、高さ、最低敷地面積、壁面の位置、かき又はさくの構造等のルールや公共空地等の確保について、きめ細かく計画を定め、よりよいまちづくりを進めるための制度です。
(補足)
柏市の都市計画決定一覧へ
地区計画の構成
地区計画は次の2つから成り立っています。
- 1)地区計画の方針 まちづくりの全体構想を定めるものであり、地区計画の目標や地区の整備、開発及び保全の方針を定めます。
- 2)地区整備計画 まちづくりの具体的内容を定めるものであり、「地区計画の方針」に従って、地区計画区域の全部または一部に、道路、公園、広場などの配置や建築物等に関する制限などを詳しく定めます。
地区整備計画は次のうち必要なものを定めます

逆井・藤心地区
- 1)地区施設の配置及び規模
地区施設とは、皆さんが利用する道路、公園、緑地、広場などをいいます。 - 2)建築物やその敷地などの制限に関すること
- ア.建築物等の用途の制限
- イ.容積率の最高限度又は最低限度
- ウ.建ぺい率の最高限度
- エ.建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度
- オ.壁面の位置の制限
- カ.壁面後退区域における工作物の設置の制限
- キ.建築物等の高さの最高限度又は最低限度
- ク.建築物等の形態又は色彩、その他意匠の制限
- ケ.建築物の緑化率の最低限度
- コ.かき又はさくの構造の制限
- 3)その他、土地利用の制限
現存する樹林地、草地などの良い環境を守り、壊さないように制限することができます
|
用途地域 |
高度地区の指定 |
建築基準法 |
対象建築物 |
日影測定面 平均地盤面からの高さ |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 第一種低層 住居専用地域 第二種低層 住居専用地域 |
容積率 50% |
- |
3時間・2時間・(一) |
軒高7メートル超 |
1.5メートル |
| 容積率 100% 150% |
4時間・2.5時間(二) | ||||
| 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
第一種高度地区 | 3時間・2時間・(一) |
10メートル超 |
4.0メートル |
|
| 第二種高度地区指定なし | 4時間・2.5時間・(二) | ||||
| 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
第一種高度地区 第二種高度地区 |
4時間・2.5時間・(一) | |||
| 指定なし | 5時間・3時間・(二) | ||||
| 近隣商業地域 | 容積率 200% |
第一種高度地区 | 4時間・2.5時間・(一) | ||
| 第二種高度地区 | 5時間・3時間・(二) | ||||
お問い合わせ先