トップ > くらし・手続き > 地域活動・コミュニティ > 町会・自治会・ふるさと協議会 > みんなで考えるこれからの地域 > 協働事業 > 町会等情報交換会 > 第14回町会等情報交換会
更新日令和3(2021)年11月2日
ページID26508
ここから本文です。
第14回町会等情報交換会
「第14回 町会等情報交換会」の報告
今年度は、「町会等でできる防災活動」をテーマとし、防災活動において工夫している点や課題について情報交換を行いました。今回も昨年に引き続きオンラインでの開催といたしました。
日時
令和3年10月1日(金曜日)午後2時から3時45分
参加者
市内町会等役員 22名
開催方法
WEB会議システムZoomにて開催
概要
主旨説明(柏市地域支援課 吉田課長)
- 日頃、町会活動を通して地域のために活動して頂いていることに感謝したい。本日は台風16号が接近し、柏市内で20 か所の自主避難所が設置されている中、「町会等でできる防災活動」をテーマに有意義な情報交換会になることを期待している。
- 江戸時代の災害現場を発掘調査した経験や日本各地での災害地の遺跡から伺えることは、住民はどの場所からも離れず復興しており、人と人のつながりは昔から大事であることの表れである。
- 本日の情報交換の場が、参加者の皆さんのこれからの防災活動に役立てて頂きたい。
防災に対する町会等の心構えについて(防災安全課)
- 避難所生活は過酷であり、避難所に行かずとも良い日頃の備えが大切。
- 自助、共助が重要であり、自助として1.食料・水備蓄、2.家具転倒防止、3.家族での避難所の事前相談(どこの?ルート等)を行う。共助は自主防災組織の取り組みで地域を守る。
- 在宅避難が困難な場合の非常持出品、避難所の備品、備蓄品を紹介。
- 避難所運営として、開錠者決定、避難所運営委員会の設置が必要。運営事例を紹介。
- 災害に合わないという思い込みを捨てる、自分たちで守る、災害時は協力することが大切。「助けられる人」から「助ける人」へ。
グループディスカッション
Aグループ
1)コロナ禍での防災活動の実態、工夫した点
・感染症対策から、この2 年間具体的な活動は実施できていない。今後、知識の拡充や情報を収集して取組む。
・「避難場所」及び「避難所」の場所を把握してもらう訓練(自宅から徒歩)を実施したところ、最寄りの避難所が遠いことも分かり効果があった。
2)町会等で取り組む防災活動(身近な防災活動)とは
・発災時の安否確認として、「無事ですプレート」やタオルを玄関先に掲げる方法は取り入れたい。
・活動を進めるうえで、向こう三軒両隣とのコミュニケーションは基本。そのため、毎月一回の青空集会(広場の草刈りやラジオ体操)を開催して顔合わせをし親睦を深めている。その際、連続して不参加の方々の扱いをどのようにするか要検討。
・防災活動の活動資金を柏市地域活動支援補助金(+10)制度で活用したい。
・柏市から発行している「柏市災害時あんしんマップ」「柏市洪水ハザードマップ」を活用することは防災活動の基本。
・避難所運営ゲーム(HUG)は有効であるが、経験した参加者はいなかった。
3)防災活動の課題
・少子高齢化、独居高齢者宅の増加により、要支援者が増えることから町会単位では対応が困難。
・新型コロナウィルス感染症拡大により、「分散避難」に対する防災知識習得、情報収集が必要。
・発災後、1 週間程度は地元町会の住民が力を合わせて避難所運営をすることになるため、町会がどこまでするのか(できるのか)を見極めた活動が必要。町会防災組織の有無、意識レベルで大きな違いが生じる。
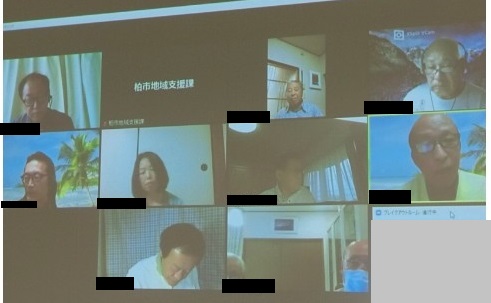
Bグループ
1)コロナ禍での防災活動の実態、工夫した点
・自主防災組織は、グループの町会等すべてある。
・防災訓練は行っていない町会等がほとんどであるが、安否確認訓練を実施または予定している町会が一部ある。
・避難所の暑さ寒さ対策は必要。備蓄は避難所にあるが、町会が備蓄しているところは1町会で食料備蓄のみ。
・K-Net は、支援者が充足し毎年安否確認をしている町会等がある一方、個人情報の観点から班長さんたちの協力が得られない町会等もある。
2)防災活動の課題
・避難所、避難場所が適所ではない。指定されていない場所が適所である場合に市役所で対応してほしい。また避難所によっては、障がい者には使い難く検討が必要。
・防災訓練を班長会議において机上で行い、その結果を住民に回覧で周知したが、どの程度認識したか不明。
・K-Net の要支援者に町会未加入者が含まれており、対応に困っている。実際はマッチングして対応しているが、行政としての考えを聞きたい。
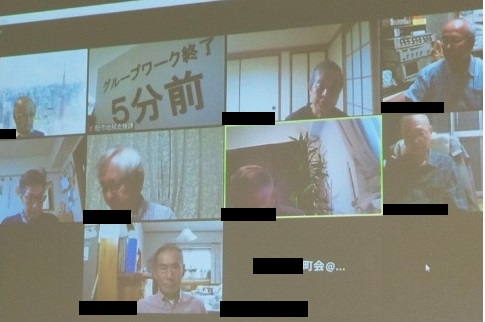
Cグループ
1)コロナ禍での防災活動の実態、工夫した点
・防災訓練は昨年度より中止している町会等がほとんど。安否確認を実施または予定している町会等がある。安否確認では要支援者が多いので検討が必要。
・消防署による防災講習会や自主防災組織によるレクチャー、防災安全展示や防災グッズの展示を実施。
・災害対応備品の準備や無線機の活用を進めている。
・防犯パトロールは月1回継続しているが、この時に道路の冠水などもチェックしている。
2)町会等で取り組む防災活動(身近な防災活動)とは
・発災後、最初の15 分が大切であり、この間に自助・共助で何ができるかの検討が必要。救助、備品整備、安否確認も、毎年班長が替わる中で、どう継承するかを考える必要あり。
・安否確認訓練は、問題のない住民は白いタオルを掲げ、これを班長が確認して、タオルがない家にはベルを鳴らすことにしている。
・講師による講演会を実施する。
・防災グッズ紹介が好評で、簡易トイレや、グッズ展示、試食会なども実施予定。
・多くの避難所が小中学校になっているが、コロナ等で学校の協力はあまり得られない可能性がある。地域にあるお寺や、区民館なども避難所として利用するようにし、備品を備える。
・避難スイッチをテーマとした講演会を予定している。どのタイミングでどう避難するかを事前に決めておくことが重要。
・消火器の設置、点検を予定している。
・熱海の災害で名簿が役立ったと聞いているので、名簿の作成を進める。
・避難所をポイントとしたウォーキングを実施し、避難所を知るアイデアあり。自宅から避難所までの道や、危険個所なども知ることができる。
・発電機を2、3 台あり、特に班長が使えるようにしている。
・災害の図上訓練(DIG 訓練)は意識向上につながり、ぜひやる意義はある。
・町会の清掃に合わせて排水溝の掃除を実施。排水溝が詰まって水があふれることもあるので、この掃除をルーチン化していきたい。
3)防災活動の課題
・マニュアルを作る必要があるが、どうしても凝ったマニュアルになってしまい、読むだけでも大変なもので、使いにくいものになってしまう。
・消火器を盗まれたこともあり、また中学生のいたずらもある。町会の所帯が大きいと難しい。
・避難所が学校だけでは問題があり、自前での避難所も準備しておく必要がある。また駐車場も確保する必要がある。
・おやじの会で避難所体験訓練を企画したが、一般の参加者はゼロであり、危機感が薄い。何かあれば避難所に行けばよいと思っている人が多い中で、自宅避難も考えておく必要がある。その際自宅が安全か、どの段階になったら避難所に避難したほうが良いか“避難スイッチ”を決めておくことが重要。
・防災活動等班長が中心となるところが多いが、班長が毎年交代する中でどう繋げていくかが問題。特に今はコロナで活動ができないのでなおさら。

Dグループ
1)コロナ禍での防災活動の実態、工夫した点
・これまでは年1 回の防災訓練(k-net 登録者の安否確認、炊き出し訓練等)を行っていた。
・コロナ禍で十分な訓練は実施できていない。
・ふる協では、防災無線を利用した通報訓練を行っている。
・班長を中心に西部防災センター(松戸市)へ視察に行っている。
・Line の普及はあるが、安否確認は人海戦術である。
・安否確認として「黄色いハンカチ」を掲示。方法を検討中の町会等もある。
2)町会等で取り組む防災活動(身近な防災活動)とは
・2000 世帯を余りの町会等であり、全体での防災活動は不十分であるため「防災プロジェクト」を立ち上げた。
・情報伝達機器がテレビからスマホに移ってきたので、発電機を購入し充電に備えている。
・週1 回、事務局が浸水対策の展示会を開催。
・マイタイムラインの作成を行い、自分の命は自分で守る意識づけを行っている。
・AED マップ、井戸水提供者名簿の配布を行っている。
・地域の事情から地震対策より洪水対策に注意を払っている。
・k-net 登録のため、70 歳以上の高齢者をリストアップ中。
・k-net 登録者に「黄色いカード」を配布。
・ご近所見守り隊を組織した(民生委員、班長、有志)。
3)防災活動の課題
・避難所として高い所が良いのか、低いところが良いのか見解を一致させる必要がある。また、学校施設の鍵保管者について誰が適任なのか検討する必要がある。
・行政が、町会毎に避難所を指定できないのか?
・電話での連絡網をLine に変更したが登録者が少ない(1600 世帯で30%未満)。
・町会員の中には公助に頼り過ぎる場面もあり、どのような対応が必要か知りたい。
【備蓄について】
・予算や場所に制限があるため、町会等での備蓄には頼らず、自助努力を求めている。町会運営のために水は用意している。
・避難所にいくらかはあるが、行政が保有する備蓄品を分けてもらうか、自助努力が必要。
・小規模町会では準備できないため、近隣町会合同で準備するモデルを準備してほしい。
・生活用水確保(飲料には不可)として、井戸水提供者と協定している。また井戸を掘った。
・k-net 登録者用に食料と簡易トイレを準備している。
・町会未加入者への対応について要検討(未加入者は誰が対応?)。
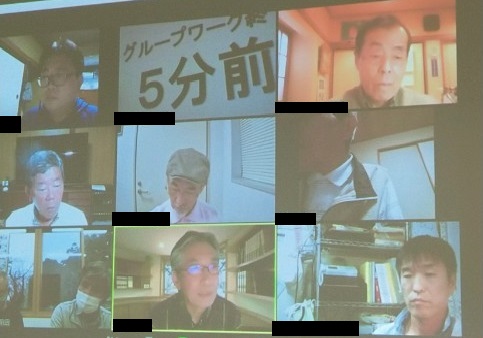
お問い合わせ先